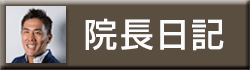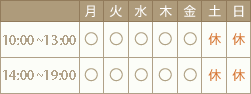噛み合わせとパフォーマンス-その5
5.経年的な噛み合わせの変化と身体の状態、身体操作の関係について。/噛み合わせと首の可動域。
(松坂選手、黒田選手、阿部選手、松井選手)
松坂選手

過去の西武時代の写真を見ると右側の犬歯が低位といって歯並びのアーチから外れた形になっています。これは乳歯と永久歯の生え代わりの時期に上顎の犬歯は一番最後に生え変わるため、生える場所がなく、この位置に生えるというよく見かけるパターンです。
八重歯といってアイドルなど笑顔の時のかわいい象徴のように言われていた時代もありました。
犬歯は噛み合わせにとって関わる筋肉の緊張、緩和に一番深く関わり、噛む位置を長期で崩さずコントロールする舵取りを担う一番重要な役割を果たすと言って過言ではない歯です。左右上下の犬歯の位置関係が正しくあることは非常に重要です。
松坂選手は右側の犬歯の関係がありません。
こうなると犬歯以降後ろに並ぶ奥歯がどう動かしても当たる状態になってしまいますから
絶えず右側の咬筋が働く形になり右目は引っ張り下げられ、下顎は右後上方に引き上げられる形になります。
西武時代の頃の写真をみても右目が下がり、下顎は右側にずれています。上の一番前の歯も右になびいています。歪みはこの時点でも強い方と言えるでしょう。
右投げの投手としては悪い歪みではありません。身体の左側には壁ができて、右に回旋がしっかりとできるうちは球の出どころのみにくい力の伝わる身体操作ができると思います。

現在の顔の歪みを見てももちろん同じ傾向です。
噛み合わせのずれが強くなってくると左端の線で囲んだ側頭筋、咬筋、僧帽筋、胸鎖乳突筋あたりが緊張して左回旋することがどんどん難しくなってくるでしょう。



くらべてみるとどうでしょう。
投げている時の表情に注目してもらうと、若い頃は右後方に下顎が引かれている傾向はあるにはありますが、力の抜けた表情で身体操作できています。
歳を重ねてからの表情にはかなりの変化が見られます。
引きつり方が強まって顎も上がっています。
これは右後方の筋群の過緊張から左回旋が難しくなっているためです。
もしかしたら左右の視力に差が出る、左目の眼圧が高い、右耳が聞こえづらいような症状が出ているかもしれませんね。腰痛や右足の内転筋がうまく働かないような症状もあるかもしれません。
これだけ右後ろに突っ張った状態で左回旋を入れるのですから自分の意図するより右に抜けてしまう球が多くなるでしょう。
ここで一つ身体操作に問題を起こす噛み合わせからの影響を付け加えます。
首の可動についてです。
アスリートにとって首の可動がいかに重要かということと、噛み合わせがいかにその可動域に影響するかを現在噛み合わせの治療をしている患者さんの調整時の状態を併せて説明するとわかりやすいので少し御紹介します。
野球で言えば、ピッチャーは投げる時構えるキャッチャーのミットに対して右ピッチャーならば左目、左ピッチャーならば右目を主として目標を捉え、首の可動を十分に使い、弓を引くように重心を軸足側に置き、ためをしっかりとつくります。
バッターであれば右打者は身体の左側に、左打者は右側に壁を作り、首の可動を十分に使うことでバットを持つブリップをしっかりと全身の力を軸足の中臀筋に溜めれた状態のトップの位置へ導き始動し始めます。
バレーボールで言えばアタックの時首の可動域を十分に使いアタックを打つ時しっかりと溜めをつくることができ、テニスで言えばサーブの時が同様の動作にあたるでしょうか。
噛み合わせが悪いと首の可動域は狭くなります。

患者さんの一度の調整前と調整後の写真で説明します。

彼女は治療途中です。今回来られた時は右胸鎖乳突筋に張りが出ていて、左は肩の後ろから背中にかけていたいという症状がありました。噛み合わせの変化を確認して調整。可動域は上がり、症状は消失しました。

彼女は初診です。大きな症状は出ていませんが、知り合いの紹介で、話を聞いていて噛み合わせからの不安に思い当たりがあるということと、マッサージを受けに行くと首、肩の張りが酷いと言われるということで調整を希望されてきました。レントゲン写真で頚椎と頭蓋骨の歪みを診ると軽い症状とは裏腹に複雑に下顎はずれ、頚椎の歪みがS字に大きく、将来の予防的な意味を強く持ち、なにより本人の希望もあり、調整をはじめました。調整後は頸部の緊張はとれて、特に右方向への首の可動域が拡がりました。

総合格闘技元チャンピオン/プロレスラーの川口選手です。
一ヶ月ぶりのこの日は右肩が前に旋回して低く身体ぜんたいが左にねじれている感じでした。
本人曰く身体の調子はよく、練習もよくできているがときどき噛んでいるとがりっと奥歯が強く当たる感じがする。という新しい症状が現れていました。
調整後右への首の可動域が上がりました。
私は治療の際、全身の状態の把握と、噛み合わせの問題になる箇所を調べるひとつのチェックポイントにつま先の開き具合を診ます。

川口選手の調整前のつま先の開き方と調整後のつま先の開き方です。
噛み合わせは足の先まで影響を及ぼすことがよくわかります。
松坂選手で説明します。

多少比較するには動作が同じタイミングではないので正確とは言えませんが、西武時代よりレッドソックス時代の方が首の可動域が狭くなり、タメや粘りといった動作ができなくなっているように見えます。
松坂選手は前述通り右の上下犬歯関係がありませんから右側咬筋の過緊張、胸鎖乳突筋、僧帽筋を中心に右側後頸筋群の過緊張から左へ回旋する首の可動域は著しく狭くなっています。それは過去の投球フォームと近年の投球フォームを比較すれば一目瞭然です。
気付かれているかもしれませんし、そうであればトレーナーにより同部位への施術が施されているかもしれません。
しかし、右側犬歯関係がないことが確認できて言えることは、このケースに限って言えば噛み合わせのアプローチなしに、状況の好転は困難と言わざるを得ないでしょう。
噛み合わせの調整で首の回旋の可動域を広げることは可能です。
同様に後に紹介する選手の首の可動域は狭くなってないでしょうか。
アスリートにとって頸部の筋肉の過緊張による運動制限がかかることはパフォーマンス全体に密な影響を及ぼします。
最近ラグビー選手から脳震盪が多くなってきたという相談を受けました。
ご存知かわかりませんがメキシコのボクサーの多くはパンチを首をひねって逃がすという技術を備えています。この技術から得れる情報は首の可動が充分になければこの技術は習得できないということです。頸部筋が過緊張を起こしている状態では首をひねり力を逃がすというような芸当は不可能でしょう。固定された頭に顎を支点に瞬発的に強い力を加えれば頭蓋骨の内部に浮いている脳はゆれて周囲にぶつかり、脳震盪をおこします。
頸部筋の過緊張は噛み合わせを正すことで解けますし、可動域も拡がります。
作成するマウスピース上でも歯が固定されてしまうような形態より、スムーズに下顎が動かせる形にして力を逃がす要素を盛り込めば、尚いっそう脳の揺れを防ぐことになるでしょう。
なにより首の可動域がしっかりと広くあるということはアスリートにとって非常に重要ということがわかっていただけたら幸いです。
松坂選手は本来、下顎の位置を頭蓋骨、頚椎、身体の歪みを取り、重心の正しく取れた位置へ戻して右側の犬歯の位置関係を正すという目的をもった治療をおこなうことが正しいと思いますが、選手ですからそのような時間もリスクもとれないと思います。
生活面で食事を取る時右噛みばかりにならないようにする。特にフランスパンや乾き物のように引きちぎる動きの入るものを右奥歯を使って噛まない。ガムなどは絶対に禁忌です。どうしてもという場合は左で噛むべきでしょう。
下顎の左側から力がかかる体癖はすべてよくありません。
うつぶせ寝は非常に危険です。仰向けで寝る場合も右を向いて寝ると思いますが、重力を受けて下顎は右にずれますから、難しいと思いますができるだけ上を向いて寝るべきでしょう。
とにかく右の奥歯でくいしばる、負担がかかる行為は生活の中で取り除いていくべきです。
そしてなにより、過緊張を起こしている首、後頭、下顎周囲の筋肉の過緊張を取り除き、頭蓋骨の歪みをほどくように噛み合わせの調整を行い、若い頃のように力まず左回旋のできる可動域の拡い頭頸部の状態を取り戻すべきです。その上で尚、噛み合う歯や緩んだ顎関節の影響を受けるようであれば、要素を盛り込んだマウスピース、もしくはテンプレート(硬い擬似的な噛み合わせを再現したマウスピース)をつくり、噛み合う歯の影響、右側の犬歯関係がないために引き起こされる問題を取り除き、右から左への重心の移動、スムーズな左回旋を生み出させるのが良いでしょう。
ここで前田健太選手の身体操作を見てもらいたいと思います。

前田選手の顔の歪みは前に紹介させていただいた選手と比較すると少し複雑で、レントゲン写真で詳細をみないと間違いやすいケースかと思います。
右目が下がり右側の咬筋が強く働いていることは間違いありませんが、下顎の位置は若干左にずれているように思います。
下顎骨の前部が左、奥が右にずれているかもしれません。
とにかく右の奥歯が強く噛んでいるのは間違いありません。
このケースは右回旋も左回旋もしにくくなる可能性があるので慎重な調整が必要だと思いますが、現段階で前田選手は身体操作において、下顎の使い方が非常に上手だと思いますので良い例として紹介させていただきます。

投球動作に入っても口が開いています。これは力みのない証拠です。
可動域も充分あります。
身体の左側にはしっかりと壁が作られ、重心が右に入る時は下顎が右に入ります。

重心が左に移動する時に下顎は左に移動します。これで左回旋がしやすい状態がつくられます。しかもこの状態でも口が開いて筋の過緊張をおこしていません。 このタイミングが早くなれば身体は開いてバッターから球が見えやすくなるでしょう 。リリース近くなると下顎が前にでます。動きを止めて身体の内側に力を込める動作(スタビリティ/ウェイトリフィティングなど運動というより固定の動作)以外は奥歯でくいしばる動きは必要ないと私は考えています。前田選手の下顎を前に出す翼突筋をうまく使う動きはハンマー投げの室伏選手なども同じです。

口は開き下顎周囲は力みません。下顎は少し前でロック、前田選手とよく似ています。
前田選手は下顎、頭頸部の筋肉の動きを非常にうまく使えていると思います。
黒田選手

黒田選手は下顎のずれ方、頭蓋骨の歪み方が複雑です。
口角が左上がり、このずれの大きさは下顎に変形がある可能性もあります。下顎の先は左を向いています。
下顎のずれは若い頃が一番顕著で時系列に並べてみるとその傾向は歳を重ねると少なくなっているように見えます。逆に特徴的になってきているのが目の大きさです。歳を重ねていくと徐々に左目より右目が小さくなってきています。下唇が右にずれていくところをみると下顎骨の高さが左が短く、前部は若干の左ずれ、後方は右にずれ、経年的に全体的にも右に横ずれを起こしているのではないでしょうか。レントゲン写真で読まないと正しくはわかりませんが。

(下顎骨が横ずれしている患者さんの頭蓋骨のレントゲン写真です。上顔面をつくる頭蓋骨に対して下顎骨が全体的に右に横ずれしています)
右投手は右に下顎を入れて身体の左に壁を作り、左に回旋をつくらなければいけません。若いときの黒田選手の顔貌は下顎の先が左に向いていて左目と口角の距離も近いことから左回旋しやすく身体は開きやすかったのではないかと推測します。それがトレーニングや長年のフォームの修正など、もちろん実戦もですが、右に下顎を入れる動きを行っているうちに徐々に下顎の位置が全体的に右ずれを起こしているのではないかと思います。そのため歳を重ねてからの写真に見られる下顎の先の指す方向は若い時ほどずれて左を差していません。
正確な詳細を知れる資料がなにもないので、すべては予測ですが。
もしかしたら歯の治療を行ったのかもしれません。
右目が左目と比較して小さいということは右側の筋肉に緊張があるということです。
右横ずれした下顎の右側奥歯に強く引っかかる噛み合わせの当たりがあるでしょう。
タイプとしたら冒頭の方で紹介した、総合格闘家の川口選手と似た下顎のずれかただと思います。(初診時の川口選手は下顎骨が全体的に左に横ずれしています)
元は左回旋をしやすいタイプですが、全体的に右にずれて右の奥歯に強い不正な当たりが生まれているような状態になると後頸部の筋肉は全体的に過緊張を起こして、本来の首の可動域は失われます。
メディアの情報でしか何も知り得ませんが、首と右肩痛で登録を抹消されたようですが、手のしびれなどは伴っていないでしょうか。
私は頭蓋骨と頚椎の歪みを診断して噛み合わせの治療を行います。
手のしびれがあるという症状は噛み合わせの治療の初診時にはよくある症状です。


この方は今も通っておられる患者さんです。
左が初診時、右は調子が上がっているので当初予定のなかったインプラント治療を望まれたので右下に施した後の時期のものです。
外耳道をイヤーロッドで固定、基準として歪みの変化を確認します。
首の傾き、ねじれ、目の位置などが改善されているのがわかると思います。
インプラントの術後どうしても手術した箇所をかばって左噛みになるので、右のレントゲン写真も頭蓋骨、頚椎共に左に傾いてしまっていますが今はもう改善されています。
退職間近になり、身体のメンテナンスをしたいから全体的に診てほしいということで通って頂いています。
40年間どんな有名な手の名医にかかっても手のしびれはとれなかったという方ですが
内容を理解していただき、噛み合わせの調整、治療に入り、4ヶ月目に完全に手のしびれは消失しました。
腕神経という脊髄神経が頚椎から出ていますので、そこの歪み、傾きをほどくことができれば症状は消えるというわけです。
この人も頚椎症性神経根症です。噛み合わせの不正から起こる問題の代表格といえるでしょう。脊髄神経が椎骨のずれで圧迫され症状が出るのですが、ずれが酷くなっていっている中、投球動作のような負担をかける動きは症状を悪化させるでしょう。
歪みをほどき、引きつける筋肉の過緊張をほどき、頚椎をストレスから解放させてあげないといけない状態になっているのではないでしょうか。
噛み合わせが深く関わっていることは間違いありません。
調整を入れて頭蓋骨、頚椎の歪みをほどき、周囲筋肉の過緊張から椎骨、脊髄神経を解放させてあげることが必要ではないかと思います。
その上で左回旋の動きをスムーズにおこなえるようにさせるのがよいかと思います。

基本的に下顎が左ずれなので、左旋回して身体が開きやすいのを右側の咬筋、側頭筋、翼突筋、胸鎖乳突筋、僧帽筋、後頸筋群、他の緊張で食い止めるのが経年的に横ずれを引き起こし、神経根圧迫を引き起こしているのではないかと予測します。
阿部選手

阿部選手は左目が下がり、下顎が左にずれています。細かくはわかりませんが右端の写真を見ると前歯部に不正な並びが見られるので犬歯の関係がよくないのかもしれません。
左端の写真と真ん中の写真とを比較して明らかに違うのは首の傾きでしょうか。
左目の高さも低くなり、より左にずれてきているようにも見えます。
左肩も下がっています。
かなり状態は悪そうです。
左バッターとしては身体の右側に壁をつくることができる、悪くない歪み方です。

しかし歳を重ねていく中で左の奥歯の当たりと引っかかりが強くなっているのは明らかです。
メディア情報でしかありませんが頚椎椎骨ヘルニアを患っているということですが、頚椎椎骨ヘルニア自体が噛み合わせを調整することで治ることはありません。しかし結局症状を悪化させるのは椎骨に負荷をかける筋肉の過緊張なので、それをほどくことは症状を軽くさせるでしょう。
また、これだけ首が傾いて見えるということは脳脊髄へかかるストレスも大きいでしょうから、副交感神経系に問題がでやすく眠りも浅くなっているかもしれませんし、内臓の調子も落ちているかもしれません。

脳底部~頸部からは左側の図の赤線に見られるように全身臓器への副交感神経系(休める働き)の神経が伸びています。
そして椎骨から伸びる神経が体表面のどこの感覚を司っているのかは決まっています。
噛み合わせが崩れると身体への問題が起きる理由の一つはこの神経系の問題です。
阿部選手の場合は左側頸部、下顎周囲筋の過緊張を緩和させ、頭蓋骨、頚椎の歪みをほどく噛み合わせの調整を施し、頚椎にかかる負担を解放させて右回旋をしやすいようにすれば良いのではないでしょうか。
ヘルニアの状態もなにも診ていないので適当なことは言えませんが、症状を緩和させることは可能だと思います。
松井選手

松井稼頭央選手の若い頃の写真と現在の写真です。
なにがどう変化しているでしょうか?
上顔面が若干左に引っ張られた感じがありますか・・・
影も入っていますし少々わかりにくいですね。
レントゲン写真で間違いのない歪みを確認したいところです。

下顎骨は若干の左ずれ・・・ 右目下がり、 頬の笑い皺は右にはいるので、歪みは左にくの字に軽く折れるようにありますが、右側の咬筋を中心とした緊張があるでしょうか。
腰痛があるような話を耳にしました。左側の腰でしょうか。


身体は繋がっています。
右の咬筋、僧帽筋、後頸筋が緊張すれば、筋膜のつながりを診て左側の腰が痛んでいるのではないかと推測します。
松井選手は下顎が左にずれていますが右の奥歯が強く噛んでいます。
両側の奥歯が強く噛んで頸部の筋肉の緊張も両側に出ている可能性があるので、そうするとどちらの回旋も弱くなります。
首の可動域は過去と比較して両側とも狭くなっているでしょう。
少なくとも噛み合わせの調整で頭頸部の筋肉の緊張をとれば今のパフォーマンスは上がると思います。腰痛に関しては絶対とは言えませんが良い変化は現れるでしょう。
なぜならば先に図で示した筋膜、他、様々な組織の流れにより身体はつながっており、頸部、下顎周囲筋の緊張は足の先まで影響を及ぼすからです。もう一つ、福島県立医科大学の発表内容によると原因不明の腰痛患者の脳血流量を調べたところ7割の腰痛患者の脳血流量が低下しているということです。この発表を受けてアメリカ、ノースウェスン大学は更に研究内容を進め、慢性腰痛患者は即坐核(脳の前頭前にある気持ちをポジティブにやる気にさせる場所)の働きが低下しているという報告をしています。通常腰部で炎症などが起こると、その痛みは脳へと伝わり。即坐核はこの痛みを制御する働きがあります。つまり即坐核が正常に機能することで人間は必要以上に痛みを感じない仕組みをもっているのです。しかし脳の血行が悪くなり、側坐核の機能が低下すると、本来抑えられるはずの痛みが抑えられなくなってしまうというわけです。
脳の血流は側坐核の機能を低下させ、腰痛を引き起こすというメカニズムです。
そして、噛み合わせが悪くなれば頭蓋骨、頚椎は歪み、傾きます。内部にある脳・脊髄の血流に影響は及ばないでしょうか。
どうでしょう。
実際に私の患者さんで、腰痛がなくなる事例はよくみる好転変化の一つです。
決して噛み合わせを正すことで腰痛の全てが治るとはいいません。
ただし、なにをしても腰痛がとれないという人は噛み合わせからの影響も疑ってみてはどうかと提案します。
松井選手は両方の打席を使いますので少し特殊です。
左ピッチャーの外角の逃げる球、外に落ちていく球は打つ必要がありません。
歪みから読めば左バッターの際は身体が開きやすく右ピッチャーのアウトコースの速い球、右に変化する球、特に身体から逃げながら落ちる球などが難しくなってきてないでしょうか。

一塁への走り出しのスピードは速くなっているかもしれません。
右打席ではインコースの速い球に詰まることが増えているのではないでしょうか。
歪みから診れば可動域が充分にあり、しっかりと回旋さえすれば右打席の方が理屈には合っています。

しかし、もしどちらも調子が上がらない状態なのであればひとつの選択として、頭蓋骨、頚椎の歪みをとり、左右回旋をスムーズに行えるように噛み合わせの調整を行うい、腰痛の変化を診てみても良いと思います。
このように長く説明してきた内容の先にはうつ病であったり、健康を害する症状を持つ患者さんがいて、それは脳脊髄が捻られストレスを受け、血流に障害が起き、リンパの流れが悪くなり、神経が圧迫されていることから起きているものと私は考えています。よく耳にするインプラント後の不定愁訴も同じ説明で言える内容で、私は主としては日々その症状改善を噛み合わせからおこなう治療を中心に歯科治療全般に携わっています。
しかし噛み合わせの治療から全てが治るものでもありませんので、自分の手の届かない関連性のあることは信頼のおける他分野の先生と連携をとり、治療、施術をお願いする形にしています。なかでもアスリートに関する身体のことはアメリカのドクターライセンスを持つカイロプラクティックの河合智則先生と連携をとらせていただいています。
不整な噛み合わせの身体への影響は大きなものです。
できるだけ予防、調整を行い、未来の健康とアスリートには今持てる能力をすべて出し切れる身体の状態を手に入れていただきたいと思います。